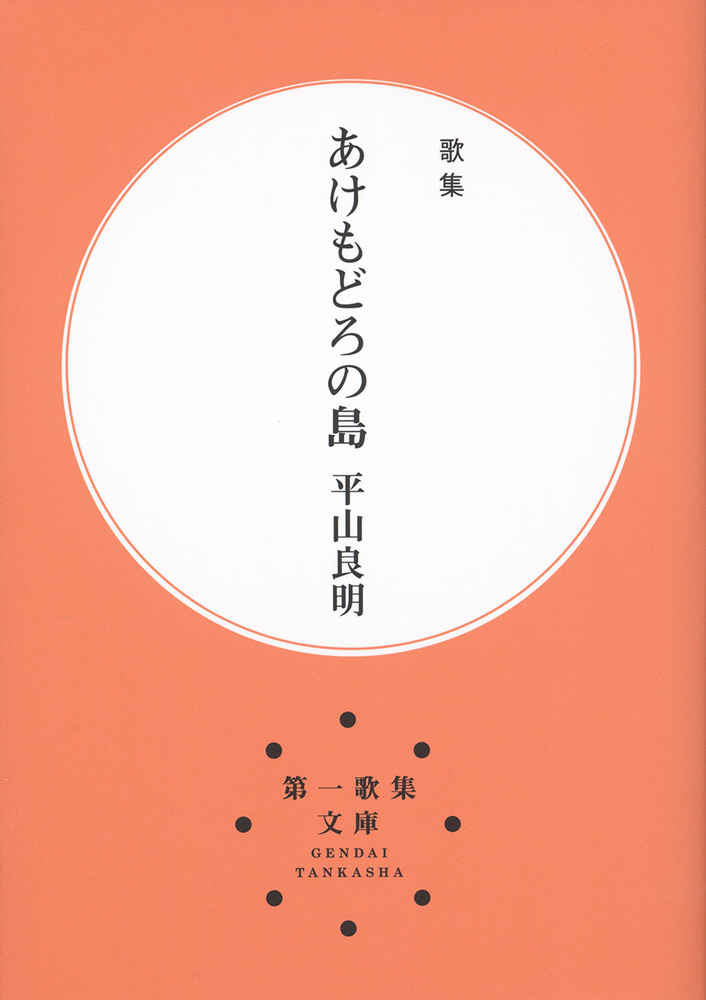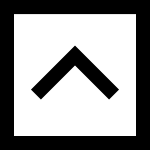平山良明歌集『あけもどろの島』が第一歌集文庫として出版された。初版は一九七二年なので約五十年前である。平山良明三十八歳。この年、沖縄は日本に返還された。敗戦後二十七年を経ての本土復帰であった。
かつて、沖縄では激烈な地上戦が展開され、実に多くの人命が失われた。日本人の死者十八万八千百三十六人のうち、沖縄県民は十二万二千二百二十八人にのぼる。この沖縄県民のうち九万四千人は非戦闘員の一般人である。にも関わらず、日本のために献身的に闘ったこの沖縄の人たちを日本軍は護らなかった。そして、五二年のサンフランシスコ講和条約で日本はその沖縄を切り捨てた。
戦後は米軍による強権的な土地収用で一方的に生活の場を追われ、その後の米軍基地の占有で治安や人権を脅かされ、日々の軍事訓練では日常の安全を奪われて、現在もその状況は変わっていない。今でも在日米軍施設の70%以上が沖縄に集中したままである。そしてまた新たな基地建設や自衛隊配備が強行されようとしている。それは、まさに屈辱と忍従の歴史でしかないだろう。
本集は、著者二十代の作品を多く収めるという。五六年、米軍の横暴な軍用地接収に抵抗した〈島ぐるみ闘争〉のなかに、青年平山良明はいた。序文を書いた仲宗根政善は「琉球大学の学生だった平山君が、壇上に躍り上って、旗をふり、音頭をとって大いに気勢をあげた」と当時を振り返っている。
・鶏頭は枯れたるままに空を向きぬ海は嘉手納の色を映さず
・鉄柵を這う如く吾等群れており腕組みながら声あげながら
嘉手納、北谷はかつて米軍が初上陸した土地である。現在の嘉手納基地は嘉手納町、沖縄市、北谷町に跨るが、その嘉手納町は面積の82%を基地が占める。枯れた鶏頭はいっせいに空を仰ぎ、海がその土地を映しだすことはない。基地は沖縄にとって巨大な異和であり、嘉手納はまさに生活を文化を侵奪された沖縄の縮図であった。
鉄柵は反対運動を阻止するために設けられたのだろう。その外側で腕を組み、声あげながら抗議活動を繰り返す市民たちがいる。かつて日本のために戦った沖縄は、今自らの生活や文化を守るための闘いに転じたのだ。
*
短歌は思想の器たり得るか。かつて歌壇でそうした論議のなされた時代があったし、今もあるかも知れない。私は短歌は〝思想の器〟たり得ると思う一人であるが、本書を読み返すとそんな議論の虚しさを感じないではない。少なくとも、沖縄の反基地闘争はイデオロギーの問題というより、人間の尊厳を奪い返すための闘いであり、自らの生活とアイデンティティを守りぬく闘いであると思う。
六〇年代、ベトナム戦争の出撃拠点とされた嘉手納からは連日夥しい数のB52が発った。かつて地上戦で猛攻撃を受けた沖縄が、その土地からベトナム出撃させることの加害者性を平山は自らに問う。この苦悩の二重性は重かったろう。平山の短歌が硬直した政治思想ではなく、文学として自己を問い返す視点を内包していることを私は貴重に思う。それは、服従とは加担することだという倫理の苦さでもある。
この島は、たえずある種の「宿命と疎外」という形で問いかけられ、受けつがれて来たのであった。自らの判断で事を企るということを許されず、たえず忍従の中から「生きる哲学」を見出し、他人と同居させられるという形式の中で、沖縄的なるものをあたためる以外に道はなかった。
本集「プロローグ」に記された一文である。それでも、分断と抑圧に屈しない精神の勁さを平山は海上に燦然とかがやく〝あけもどろ〟の空に見ていた。それが古来父祖たちの育んできた〝太陽の思想〟なのだろう。さまざまな同化政策に妥協も同調もせず自らを恃むには、沖縄に固有の精神に拠って立つしかない。
しかし、平山はその沖縄を「歪んだ不思議な島」であるという。そこに育った平山の顔も考えも歪んでおり、その平山の睨む本土もまた大きく歪んでいる。そしてそれら歪んだ交点に生まれたのが平山の短歌であるという。「宿命と疎外」に翻弄された沖縄がその歴史のなかで屈折し歪まざるを得ないのは自明であり、そこを故郷とする平山も本土の評価軸からみれば歪んでいるとする逆説も頷ける。政治とはどこまでも狡猾である。最も醜悪に歪んでいる政権は、情報操作によって自らの正当性を偽装する。平山はますます顔を顰めざるを得ない。しかしそれら歪みの交点にこそ、問題の所在はより濃く凝っていたと見るべきだろう。
・山羊だけが試されてあり秘めてある毒ガスの森をかたわらに見る
・沖縄の毒ガスをみなここに積み上げて戸惑わせてん皇居前広場
当時、極秘裏に知花弾薬庫に貯蔵されていた毒ガスの総量は一万三千トンに及ぶ。ふと青年の脳裏を掠めた凶行を過激とは思わないのは、それが沖縄県民の忿りの総和と見合うからだ。「空にB52、海に原潜、陸に毒ガス」とは当時の沖縄を象徴する。戦争責任を問われることなく延命した天皇ばかりではない、この仮想テロは沖縄の戦後を理解することなく日本の防衛のためには基地負担もやむなしとした大多数の日本人にも向けられていたはずである。
・きみ達にかかわりなくて今もなお沖縄島は犯されつづく
・近づけばなおも遠い母国と知る新聞は見ないで寝ることにしよう
本土との意識の乖離は絶望的に大きかったろう。当事者性の欠如と世俗の無知に真実はただ孤立を深めざるを得ない。私は本稿ではあえて「本土」と表記しているが、平山は「母国」「祖国」と書く。そして平山短歌には「人間」という語が頻出する。それは、平山の希求が人間の根源に根ざすことを推察させるに余りある。
・濃く咲けば餓死の前ぶれと伝え聞く仏桑花【あかばなー】この年は格別に赤し
この一首は、沖縄返還目前の第二版で加筆された「近づく五月十五日」二十二首の冒頭にある。まず、この一連が本土復帰の歓びに遠いことに注意したい。仏桑花の赤はなにを象徴しているのだろう。戦後、地下壕で生き埋めとなった人たちの慰霊に植えられたとも聞く。餓死の兆しとは、復帰後の時代の暗澹と混迷の喩ではなかったか。
私たちはこの一冊から何を学ぶべきだろう。平山翁すでに八十六歳。戦後、ひとりの青年が闘いつづけた六十有余年の歳月の中で、おそらく平山を支えた唯一の武器は〝あけもどろ〟に象徴される「太陽の思想」であった。それは、沖縄の歴史の育んだ精神の豊穣が身体の隅々に染みわたり、手渡してはならぬものを、護り続けねばならないものを総身に刻んだのだろう。私は知らずに過ごした歳月の重たさを恥じる。語られることの少ない沖縄史の暗部や、そこに生きた人々の肉声や体温の明るさや苦しさを知らずに語る〝戦後〟とは何であったのか、もう一度考え直す時期なのではないだろうか。
(現代短歌2021年7月号掲載)