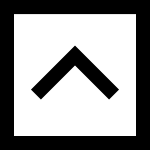天河庭園の夜
福島泰樹

再生の熱情 小野田光
『天河庭園の夜』は福島泰樹の第三十三歌集。福島は一九六九年刊行の第一歌集『バリケード・一九六六年二月』(新星書房)でのデビュー以来、二年に一冊以上のペースで歌集を発表している。早稲田短歌会で作歌を始めてまもなく六十年。創作意欲の源には一貫して亡き者たちへの溢れる追慕の情があることは、今さら言うまでもない。本書も岡井隆、哲学者の桶本欣吾、岸上大作ら故人へ歌を捧げる構成となった。彼らへ寄せる思いを通じて、過ぎ去ったはずの過去が現代に聳え立つ。再生された時間にありありと触れることができる仕掛けはどういうものなのか。 ・歌集『天河庭園集』の一巻を ひどく激して纂みしこの俺 本書名は岡井隆の歌集『天河庭園集』に因んでいる。同歌集は一九六七年から七〇年までの歌をまとめたもので、もともとは独立した歌集ではなく、岡井が九州への出奔中に刊行された『岡井隆歌集』(国文社、一九七二年)に部立ての形で編まれた。福島は岡井の許可を得てそれらの歌を並べ直し、連作ごとにタイトルを付すなど「六〇年代後半の、岡井隆という個人史を抱えたその人の、あの時代との拮抗、苦闘の痕跡」を浮かび上がらせるための試みを行っている。一九七八年に岡井自身が再度編集し直した一冊が国文社から刊行されているが、福島には『天河庭園集』に対する強い思い入れがある。 本書は、一九七五年暮れの岡井との「六年振りの再会」の思い出から始まる。そして、翌年の幻の同人誌「IF」制作の打ち合わせ。福島の既刊著書でも触れられている愛鷹山麓柳沢(当時の福島の居住地)でのエピソードだ。 ・鳥打帽、トレンチコート、革鞄デビッド・ジャンセン逃亡の歌 ・「IF」は、「異府」「異父」とも書くさ「異婦」はどうDr.Ryuの顔赤らみにけり ・プレハブの書斎のめぐり水は満ち悲痛な声の耳朶より去らず 一首目、岡井の洒落た装いが目に浮かぶ。デビッド・ジャンセンはテレビドラマ「逃亡者」の主演俳優。逃亡する医師役を演じた。出奔した医師という岡井の境遇も塗す。二首目、十五歳上の大歌人との軽妙なやり取り。語呂合わせ的修辞も福島の真骨頂。三首目、近隣の黄瀬川が氾濫寸前で帰れなくなり、自分を待つ患者を心配する「声」に岡井の医師としての顔を描く。 本書前半の岡井との七〇年代の思い出は、場面活写のような歌が多いが、その鮮明な思い出は六〇年代への思い入れが基礎をなす。六〇年安保闘争以降の学生闘争と、当時、それに対して岡井が短歌で示した連帯の意。一九六二年に大学で作歌を始めた福島は、当時の「短歌会の部室は、『政治と文学』をめぐって熱く燃えていた」と振り返り、六〇年安保闘争と七〇年安保闘争に挟まれた日々、すなわち福島の大学在学期あたりを以前から「待機の青春」と呼ぶ。 ・戦後死人伝中の一人アイザック・K痩せたペダルを漕いでゆきにき ・あれからや六十年の歳月が岸上大作ずぶ濡れて立つ ・解剖をのぞむと書きし絶筆を揶揄して「土地よ、痛み」とやせむ その後、岡井とは「長く交友は絶え」ることとなるが、その理由を示す歌とともに、七〇年代の岡井の存在を通して一九六〇年に自死した岸上大作へと交差していく歌を散りばめる構成に、福島という一人称によって貫通した「待機の青春」の物語を感じる。一首目、「アイザック・K」は福島編纂の「天河庭園集」の冒頭に置かれた短文にも登場するが、岡井が岸上を表した呼称。二首目、「六十年の歳月」は六〇年安保と岸上自死の年である一九六〇年から数える。三首目、「絶筆」とは岸上が死の直前にしたためた一万字の「遺書」で、岸上はそこに「岡井隆さんに解ぼうしてもらったらわかる」と記している。岡井の第二歌集は『土地よ、痛みを負え』。 本書後半の岸上への挽歌は、福島の亡き者への連帯の思いが共感と拒絶との激しい渦の中に存在しており、その迫力に圧倒される。 ・「意志表示せまり声なき声を背に」自歌を刻んだ君の墓だよ ・民衆の側から常に発語した小さな葦よ 震える葦よ ・貧困も家族の不和も帰結するところはすべて「戦争」である これらの歌で福島は岸上の生に深い理解を示す。福島は物故歌人二十九人への思いを綴った自著『歌人の死』(東洋出版、二〇一五年)では、五人だけ実際に会っていない歌人について書いた。岸上はその一人ということからも、福島のこだわりは明白だ。また、近著『「恋と革命」の死 岸上大作』(皓星社、二〇二〇年)は、岸上についての入念な調査のうえに書かれた評伝。それだけに理解しがたい部分への拒絶も激しい。 ・純潔は償いならず 縄を綯う母は貧しく汗まみれなる ・美しく聡明なひとあらわれよ戦争未亡人 母捨てるため ・ならば聴く母を残してなぜにまた卑怯未練に生くべきが人だ いずれも、夫を大戦で亡くし、息子にも先立たれた岸上の母へ寄せるシンパシーから、将来を嘱望された学生歌人への厳しい言葉が並ぶ。一歳で母を亡くした福島からの、六歳で父の戦病死を経験した岸上への母親についての問いが鋭い。一方で、岸上やその母への強い連帯により、福島自らに二人が乗り移ったかのような一人称を駆使した歌も見られる。 ・「岸上家先祖之墓」を造らぬは死後は離れて暮らしたきゆえ ・死後もなお続く確執 河原から運んで置いた、朝の日射すな 岸上の母が確執のあった義父と同じ墓に入りたくないという気持ちを生前持っていたと想像し、当人に成り代わったようにさえ見える詠みぶりだ。そして、岸上本人についてはさらにその度合いが増しているように見える。 ・「恋と革命」夢敗れて死んでゆく筋書きならば冷静に書く ・ガラス一枚へだてて冬の雨の降る向かいの窓の 灯【あかり】よ消えろ 一首目は「遺書」を書く動機を描写しているが、書く者の独白のようにも読める。二首目は自死の直前、隣家が寝静まってから首つりを実行しようとする様子を「遺書」に取材し、生々しく描くが、結句は岸上本人の叫びに思える。亡き者への強い連帯が一人称文学である短歌の主体の揺れを生むことは、まさに亡き者が生身の歌人を通して現代に再生する瞬間である。 もちろんこれらの歌が生き生きと立ち上がってくるためには、どうしても福島の追慕の情の背景を知る必要がある。例えば岡井との交流は巻末の散文(本誌二〇二一年七月号への寄稿文に加筆したもの)を読むと理解しやすくなるし、二二七首の歌に対して付された七十七の詞書が短歌を補足もしている。このような構成で貫かれる物語を前に、福島編纂の『天河庭園集』のあとがきとして岡井が寄せた文章を思う。岡井は福島への謝辞とともにこう書いている。 ・伊勢とか土佐のような昔の物語を読んでいると、歌と散文とが、お互いに相手を愛し合っているめでたさを羨しく思う。(中略)歌は、実は、詞書抜きでは成り立たない表現方式かもしれないのに、わたしたちは一行の歌をたくさん並べて、読者に向って、苛酷な理解を迫っている。そんな気がする。 その後、一九八〇年代以降、岡井も福島も詞書を積極的に駆使していく。 自らの溢れる追慕の情を媒介し、韻文を主体に散文を付して過去を現代に再生する福島泰樹。一九六〇年から届く物語を通して、あらためて福島の熱情を堪能できる一冊である。 (現代短歌2022年1月号掲載) *『天河庭園の夜』は皓星社刊
続きを読む