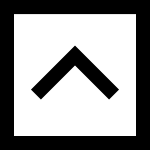輪をつくる
竹中優子

乾いた輪 小野田光
・スタンプを母が送ってくる夕べ「ギャハハ」と笑い泣いている顔の ・月曜日 職場に来られぬ上司のこと上司の上司が告げていくなり ・歌会に座っていれば自己愛の強さを指摘されている人 竹中優子の第一歌集『輪をつくる』は、親族の生き様や職場の状況が多く描かれている一冊だ。そこにごく稀に短歌のことが詠まれている。そう紹介するとオーソドックスな構成のように感じられるかもしれないが、最初から最後まで独自の視点が貫かれた歌集だ。その視点は冒頭に挙げた三首のように、過剰な叙情を含みがちな類の歌語は用いずさらっと現実を提示される。竹中の歌には、心情ではなくただ状況を詠んだものが多く、そのどこか突き放したような味わいが、湿った世界を乾かしていくような効果を挙げ、独自の視点を切り拓く武器となっている。 特に驚くのが親族へのまなざしだ。親族についての歌がこの歌集の約二割を占めていることからもわかるように、竹中は家族を描くことに心を向けている。 ・駅前のうどん屋を兄はあわく褒め母は嫌いと言う日曜日 ・松たか子の写真が飾られていた部屋に電話をかければ父親が出る ・部屋に来てテレビつけ寝ころぶ週末に真水のように老ける妹 ・いかにも一千万円貯めていそうな人だったベランダに祖母をふいに思いぬ ・鼻だけを逆向きに描く弟の人間の絵が賞をもらった この歌集で描かれている家族は、決して円満なものではなく、両親の離婚後、父親とは疎遠になっていたことなど示されている。また、作中主体と母親との関係にも困難はあるようだ。その上で読んでいく。一首目、同じ家族であっても価値観は違うということだろう。食べ物の好みの差異はどの家族でも、特に親子ではよくあることだろうけれど、「日曜日」の体言止めがその差異を明るく照らすようだ。「兄」の主張は「あわく」なされているが、「母」は「嫌い」と強く言い切っているところにユーモアを感じる。二首目は「松たか子の写真」が、三首目は「真水のように老ける」が、四首目は「一千万円貯めていそうだった」が、そして五首目は「弟の人間の絵」そのものがそれぞれ秀逸で、親族たちの個性をあぶり出している。先に述べた両親の離婚や母との不和だけでなく、父の病やおそらく入院費を巡る金銭的対応などシビアな場面も多く描かれているが、竹中の乾いた文体がそれらの問題をただ暗いものにしない原動力になっている。逆に家族への適度な距離と愛情を保とうとする表れのようにも感じる。 ・体重を話したりする風の日のとおい家族が顔を合わせば ・昏く深く腹を見せ合いながら泳ぐ 太めと言われて妹は笑う ・父親の体臭のように秋は来て少し瘦せたと笑っていたり 例えば、これらの歌には「家族」と言えば「体重」といった連想が成り立つ。一首目と二首目は同じ連作で続けて置かれているが、三首目は「痩せた」のが親族かどうかはわからない。しかし、歌集の前半で一、二首目を読んだ後に出会うと「父親の体臭」が「痩せた」という体重関連のイメージを引き連れて来たかのようにも感じ、寂しい「秋」も独特の親族の比喩によってどこかユーモラスに思える。 このように歌集の約二割を占める親族の歌が、冒頭から最後まで満遍なく配されていることで、読者は徐々に彼らへの親しみを覚える。あ、またお会いしましたね、というように。こういった既視の増幅が親しみに変化していくことで、歌集を読む楽しみが生まれる構成になっている。そういう意味では、職場の後輩である「古藤くん」の登場も効果的だと言えるだろう。 ・残業を嫌がらなくなった古藤くんがすきな付箋の規格など言う ・シュレッダーの周りを掃いている我の隣に古藤くんじっと立つ 歌集の前半では、オフィスでの「古藤くん」の様子が主体と距離のある状態で描かれている。しかし、後半ではぐっと距離が縮まっているから、読んでいて思わず嬉しくなる。 ・口をきいてくれなくなった女子のことを椋鳥の目で古藤くんが話す ・「ごはん系がいい」とポテトチップス選びつつ東京に行くという古藤くん ・理性と利害まちがえる耳ひからせて東京で会う約束をする 縮まった距離も独特の視点から描かれる。一首目は前掲の「付箋」の歌に比べれば立ち入った話題と言えるが、そもそも「すきな付箋の規格」と「口をきいてくれなくなった女子」はどちらもすごい切り口だ。二首目はお菓子の話題だが、甘くないお菓子は「ごはん系」という発想を切り取るあたりが鋭い。そして、「東京に行くという古藤くん」に三首目で「東京で会う約束をする」ところで「古藤くん」の出番は終わるのだ。読者としても彼にまた会いたいという余韻を抱いてしまう。独特のドライな文体が癖になるが、読ませる構成にも唸る。 親族と職場はこの歌集の二大要素だが、竹中は親族について書いた詩の投稿を通して今年、現代詩の新人賞である第六十回現代詩手帖賞を受賞している。授賞者の発表号である「現代詩手帖」二〇二二年五月号(思潮社)には、妹の借金などをモチーフにした「冬が終わるとき」という詩を発表した。この一編の詩には職場の「お茶代の管理の仕方」についても書かれている。歌集でも目にしたことを思い出す。 ・借金は返す気持ちが大事だと母は言いたりあれは若い声 ・派遣さんはお茶代強制じゃないですと告げる名前を封筒から消す ・お茶代にお湯は含まれるか聞かれたりお湯は含まれないと思えり 一首目は妹の「借金」かどうかはわからないが、親族のものであることは暗示されている。二首目と三首目は職場での「お茶代」の管理の仕方についての歌だ。一見すると金銭的重みに差がありそうな「借金」と「お茶代」が同じ歌集に同居することによって、どちらも誰かの気持ちを揺れ動かすものという点では同じだという、竹中の金銭への考え方を示しているようにも思う。そういう意味では、「親族」も「職場」も、金銭の循環の根本であることに気づく。 竹中は二〇一六年に第六十二回角川短歌賞を受賞しているが、いわゆる保健室登校の高校生を主体とする受賞作「輪をつくる」は、歌集の中で比べると、職場で働く社会人よりも主体の年齢が若い設定になる。そのことが、社会人になる前からとっくに社会の難しさに直面している若者の姿をより鮮明にあぶり出した。その生きにくさを乗り切るには、やはり湿った世界を乾かす武器が必要なことも一貫している。 ・目を伏せて歩く決まりがあるような朝をゆくひと女子の輪が見る ・マスカラのだまが揺れている なりたくはないけどかわいい女友達 ・女子が輪をつくる昇降口の先、花はひかりの弾薬庫として 例えば、このように同性の「輪」や「友達」への距離の取り方にも独特のドライさがある点は親族への対応と同じだ。 親族と職場。社会人と高校生。竹中の描くこれらは決して対比ではない。循環やつながりだ。その中に生の継続が描かれているのではないか。循環やつながりを「輪」とするとき、生に付きまとう重苦しさを振り払うための、まさに生きるための乾いた視点が必要なのだ。 (現代短歌2022年9月号掲載) *『輪をつくる』は角川書店刊
続きを読む