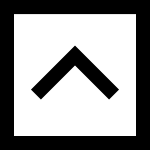森へ行った日
川本千栄

過去と勇気と安心 小野田光
・もう何年私は待っていたのだろう遠き遊びのような会話よ ・水を遣り続けた毎日本当は花を愛していたんじゃなかった 川本千栄の短歌からは、なぜにこんなにも勇気と安心を与えられるのだろうか。どの歌からも作者の人間性が立ちのぼり、その像からは安心を感じる。つらく感じる歌も多い中でどこか安心する。誰かの人生に触れることは文芸に接する読者の喜びのひとつだが、川本の歌はそういった読者がそっと自分を重ね、安心できる距離感にあると思う。また、人生を長いスパンで捉え、よく過去を振り返っている。自分を省みている歌の数々だ。未来志向という言葉もあるが、私たちは過去を振り返ることをどこか恐れる。過去には傷があるからだ。そんな私たちの心に川本の歌が安心感をもたらしてくれるとすれば、過去に目を向ける勇気があるからではないだろうか。人間はそういう勇気を持てるのだと。「遠き遊びのような会話」も「水を遣り続けた毎日」も決して後悔だけではないのだと。 『森へ行った日』は川本の第四歌集。二十九歳で作歌を始め、三十六歳から四十歳の作品をまとめた第一歌集『青い猫』(砂子屋書房、二〇〇五年)は結婚、出産、父の死などを詠んだ歌が多く、第二歌集『日ざかり』(砂子屋書房、二〇〇九年)は子育て真っ盛りの四十代前半の日々の格闘を、第三歌集『樹雨降る』(ながらみ書房、二〇一五年)では師である河野裕子を亡くし、自らには大病が見つかる四十代後半での命との向き合いを示す。そして、『森へ行った日』では、五十代に入って喪失したものがあることに気づき、新しい時のフェイズに自分がいることを自覚している感覚が印象的だ。 ・満開のまだ一片も散らぬ花 生きている人は去って行く人 ・死ぬのかもと思った時から私の生の後ろ影伸びて行きたり ・知らぬ間に五分の一が過ぎている二十一世紀もう初頭でもない 一首目、散る前の花と生きている人間を結びつけた感覚が未来という時の必然を呼ぶ。同時に過去の経験を冷静に見るところから生まれた未来への視線も感じる。二首目、大病を得た過去から自らの肉体の滅びの予感に接した痛切さが立ちのぼる。三首目の時の流れは、自らの余生を思う感覚とも関わってくるだろう。これらの歌からは、生や死と時間軸の問題が浮き彫りになってくる。過去に生きてきた時間と死に向かっている時間が同じものだと知っている人間の迫力。未来を考える時にしっかりと過去を見つめる視線が、実感と客観性の見事なまでに並立する文体を可能にしているのだと思う。 初夏の陽に息弾ませているわれに後半生のごとき藤の香 この歌集は、川本の五十一歳から五十八歳時の歌が収められており、いわば人生の後半に差し掛かっての歌集とも捉えられるだろう。五十代は徐々に死を本格的に実感として捉えられる感覚が備わってくる時期だとも解釈できる。大病を経験したことにより、その度合いが増しているとも言えるだろう。しかし、それ以上に、やはり積み重ねてきた過去を感じ、それを省みる視線に着目したい。たとえば家族との過去。 ・アッアッと言ってあめんぼ指差した水辺の吾子よ過ぎ去った君 ・ムシキングのカード遊びをしていたが虫を怖がる高校生の息子 ・幼な児はどこにもおらず二十六半のスニーカー玄関に有り 高校生になった「息子」の歌だが、いずれも現在の視点から幼少期を追憶している。一首目、かつて「あめんぼ」を必死で追っていた姿は、おそらくいまはもうない。しかし、その面影は残っているのかもしれない。二首目、幼少期から一転「虫を怖がる」「高校生」になってしまった変化。三首目は「二十六半のスニーカー」が物理的に「幼な児」の不在をくっきりと示す。これらの過去と現在を往き来する様子に、川本と「息子」との関係性の変化と喪失を感じる。 以前からの川本短歌の読者であれば、第一歌集での妊娠・出産や、第二歌集以降の子育ての喜びと葛藤を歌集で味わってきたことだろう。そういう読み方からも通史を感じられる。第二歌集『日ざかり』にタイトルにもなったこんな歌がある。 ・日ざかりに出でて遊べば子はもはや芯無く揺れる幼児にあらず 「子」がおそらく幼稚園児の頃の歌と思われるが、ここでもすでに過去となった子供の姿に思い及んでいる。成長とは消えて戻らない日々の積み重ねであることは、すでに四十代前半の川本の歌にも見て取れるのだ。子育ての歌だけを見ても、川本が過ぎ去った時間を大切にする歌人であることがわかる。 子育て以外にも、過去の歌集から常に詠われている題材はある。たとえば、教師の仕事もそのひとつだ。特に「水滴―一九九〇年冬」の一連での追憶は胸に迫る。 ・ルール守って登校しろとわれが言い登校できなくなりし女生徒 ・何のためにあんなことを言ったのか 五年の歳月ののち問われたる ・元生徒二十二歳なり登校の注意をわれがした時の年 ・わがために彼女が使った歳月は たとえ償いたいと思えど これらは川本が二十二歳の時の発言を二十七歳になって相手の生徒から咎められた場面を詠んだ歌だ。二十二歳と言えば、おそらく新任教師時代なのだろう。なぜ約三十年の歳月を経て、そのことをいま振り返っているのか。過去の歌集ではなく、この一連が今歌集に入ってきたのはなぜか。近年、過去の傷と向き合う契機があったのかもしれない。それは読者にはわからないが、ここでもやはり川本が過去に目を向けつつ作歌を行なっていることは確かだ。歌集に収められた教師としての現在の姿と併せて、職業人としての歴史を感じることができる。 子育てをし、教師の激務をこなし、歌人として作歌も評論活動も行う。そういった川本の通史の中でも、現状として捉えられるのは次の歌なのかもしれない。 ・命削って働いているねと言われたり近頃それが比喩でもなくて ・ああしんどいでもがんばると声に出し何をがんばるつもりか私 ・なまものであれば身体は腐るゆえ梅雨あめの中検診へ行く 「何をがんばるつもりか」は自分でもわからなくなるという感覚こそ、人間の原動力の源には潜んでいるのではないかとハッとさせられる。親として、教師として、そして歌人として、常に全力でがんばり続けてきた真摯さの積み重ねを感じずにはいられない。 短歌から作者が省みる過去を感じることは、言い換えれば歌や歌集の余白からも歌人の生き様を感じることである。そして、私たちはひとりの歌人が身を置いた長い時の流れに、感銘を受け、励まされる。そして、そのことにより何よりも安心する。繰り返すが、それも歌集を読む喜びである。大河小説とはまた違った長い時の流れの感慨を、たった一首から、数首が並ぶ連作から、そして一冊の歌集から感じることができるのだ。『森へ行った日』はまさにそんな短歌らしさを実感できる歌集だ。 なぜ人は見た夢のことを語るのか再び出会えぬ景色のように 「見た夢」もすでに過去である。「再び出会えぬ景色」を書き残してくれる歌人がいることは、短歌の読者にとって喜びであり、至上の安心なのである。 (現代短歌2022年5月号掲載) *『森へ行った日』はながらみ書房刊
続きを読む