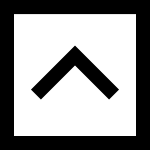夜祭りのあと
雁部貞夫

明るさと理性 小野田光
雁部貞夫の第七歌集『夜祭りのあと』は、二〇一四年から二〇一八年までの作品が収められている。コロナ禍前の歌ということになる。 言うまでもなく雁部は登山家としても広く知られ、これまで多くの山岳詠を発表してきたが、昨今、その作歌に少し変化があったようだ。本書のあとがきで、雁部自身はこう書いている。 ・二〇〇三年のヒマラヤ行をさいごに、すっかり「山行」とも縁が遠くなり、「実景はすべて歌の種」となるという子規の言葉をモットーとして来た私も、歌の材料に苦しむようになった。 現在八十三歳の雁部は、中学時代にアララギの歌会に初めて参加し、十代の終わりでアララギに入会。多くの山の歌を発表し、第一歌集『崑崙行』(短歌新聞社、一九八九年)から第五歌集『山雨海風』(砂子屋書房、二〇一六年)までに収められたヒマラヤ等の山岳詠一〇〇〇首以上の集成『わがヒマラヤ―オアシス・氷河・山々』(青磁社、二〇一九年)も刊行している。 山岳詠が代名詞でもある雁部が、山へ行かなくなって何を詠むのか。まず、身近な友人や大切に思う先達との交流を題材とした歌が頻出。登山の際の当地の人々との交流を歌にすることも大切にしてきた雁部らしい。また、次のようなユーモアをもって物事を見る眼差しも健在だ。 ・ゆくりなく京都にて見し「御堂関白記」氏の長者も裏紙に書く ・陽水の歌は好めど歌詞はダメ「金属のメタル」で「川沿いリバーサイド」か ・酔眼にゆがめる月か気が付けばマイク握りて陽水の歌 一首目は本書の巻頭歌。陽明文庫所蔵の古文書を見て、藤原道長ほどの人物が、現代でも節約の象徴である「裏紙」を使っている点に着目するおかしさ。二首目は井上陽水の一九八二年のヒット曲「リバーサイドホテル」の歌詞に不満を述べ、しばらく後の連作では三首目のように自ら陽水作品を歌っている。よっぽど好きなのだろう。本書に点在するこれらのユーモアには雁部自身が時を楽しんでいることが表れ、歌集全体を明るくしている。 時を楽しむという点では、それが飲食の歌によく表れているのが、近年の雁部の歌の特徴でもある。『わがヒマラヤ』と同年に刊行された第六歌集『子規の旅行鞄』(砂子屋書房、二〇一九年)と同様、本書でも飲食の歌が全体の二割強を占めている。 ・本郷の真砂の坂を上りゆくビルの狭間に今宵の酒場 ・朝採りの筍たきしを嚙みしめる豊かに香る木の芽とともに ・ゆつくりと酔ひが体を満たしゆく至福の時と言はば言ふべく ・黄泉にゐる小高よ今宵盃を乾せ稀なる酒ぞ会津「奈良萬」 本郷真砂坂の酒場での時間を詠んだ連作から。酒から醸し出される豊かな時の流れに誘われ、どの歌の情景にも引き込まれる。四首目は美酒を味わう刹那、亡き友小高賢を思い出し語り掛ける優しさが、いい酒だということを思わせる。読むだけでこちらまでいい気分になっていくような読後感は、正確な描写と心地よい韻律、偽りのない心情とのリンクから生まれる。 食べ飲むことが楽しそうな雁部の歌の数々だが、一方で飲食に対して自制が働くところにも、欲求との自然な向き合い方が垣間見える。 ・「食欲は理性に従へ」と古人言へど凡夫の吾は蟹【ずわい】むさぼる ・どの坂も目につく店は「飲」と「食」嫌な言葉だ飲み放題は ・昼は鮨夕べに食すステーキか子規の食欲思ひつつ食む 一首目は思わず笑ってしまうが、「食欲は理性に従へ」は『子規の旅行鞄』にも「アペティプス・ラシオ・オベイディエン」というラテン語訳で連作タイトルとして登場していた。二首目も『子規の旅行鞄』の〈「食べ放題」の朱の文字繁き食堂街いやな言葉だ「食べ放題」は〉という歌を思い出させる。まさに「理性」と「放題」は相容れないわけだが、三首目は自分の食欲を敬愛する正岡子規のそれに重ねており、自らを納得させるための言い訳のようでもあって微笑ましい。自分を戒めつつ許すような感覚もまた、理性の賜物ではないか。 ・「おまかせ」の握りそれぞれ旨けれど終の一貫焼き穴子よし ・旨き物さいごに食らふわれの性貧しき性と自ら思ふ 並んで置かれたこの二首にも同様の感覚があるように思う。いずれにせよ、欲求と理性の間を行き来してこそ、飲食の品格は保たれる。 この明るくどこか楽観的な上品さは、古希を迎えた雁部自身の過去の記憶との向き合い方にもあるように思う。実兄の病床を見舞った連作にもその一端は表れている。 ・山も歌もこの兄ありて吾のありベッドに小さく眠りたまへり ・兄のため延命水といふを汲む遥か立山よりの伏流水か ・業界の親善野球盛んなりき広岡ばりのノン・ステップ・スロー真似ゐき兄は 山と歌という雁部にとってかけがえのない要素は兄とともにあった。そんな大切な兄が弱りゆく姿を詠んだ六首の連作だが、三首目がその最後に置かれている。「広岡」とは東京六大学野球で活躍し、一九五四年にプロ野球の読売巨人軍に入団した広岡達朗のこと。早稲田大学教育学部では雁部の七年先輩に当たり、大学時代から華麗な守備で知られた遊撃手だ。そんなスター選手と兄のプレーを重ね、憧れの兄の元気だった頃の姿で連作を結ぶ。前向きな記憶との接し方をもって現実に対処する理性に心打たれる。 最後に、山のことにも触れないわけにはいかないだろう。ヒマラヤから遠ざかっても、雁部の心はやはり山々の稜線をなぞっている。 ・山へ行きミシミシ水を飲んでくるこの簡明を吾は愛せり ・ヒマラヤに行かずなりたる十余年氷斧の光いまだ保てり ・山語りあつといふ間に日の暮れか語り尽きせぬ山国日本 ・ヒマラヤに友うしなひし日の如く夕茜こき東京の空 ・齢八十記念のダルコット峠越え闘志消えねど吾が脚重し 一首目と二首目にはいずれも山の記憶と衰えぬ山への情熱が溢れる。三首目はその記憶と情熱を傾けて山について語り合う楽しさと喜び。そして、四首目はその豊かな時間の根底には、雁部自身が背負う悲痛な記憶があることを示している。雁部は一九六八年のチトラル行で同行した二人の山友を亡くしている。第一歌集『崑崙行』にはその際のことを詠んだ〈行方絶ちし友らの名をば呼ばひつつ凍てし氷河にひとり立ちゐつ〉などの歌も収められている。半世紀の時を経て雁部の心に深く刻まれている痛恨の記憶は、雁部の山への愛の一部を成していることに改めて気づく。ここにも山への果てしない欲求と、大自然とそこに眠る友への畏敬を忘れない情念があるのではないかと想像する。五首目にも燃え盛る情熱と現実に向き合う理性が同居する。事物と感情の正確な写生によって表出された欲求と理性が清々しい。 ・敗戦も原発事故も省みず「庶民」の英知またまた不発 ・かかる歌会も「数十人ホテルに何か企む」と訴へらるる日もやがて来る 本書にはこれらのような実直な表現と批判の精神により鋭く世相に迫った歌も多い。雁部が戦争とコロナの日々をどう生き、どう詠むのか。第八歌集を心待ちにしたい。 (現代短歌2022年11月号掲載) *『夜祭りのあと』は青磁社刊
続きを読む