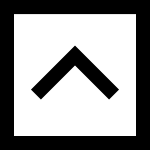花
奥田亡羊

空と花のあいだ 小野田光
奥田亡羊は自身の第三歌集のタイトルの由来についてあとがきにこう書いている。 読み返して花の歌が多いので歌集名は『花』とした。 確かに「花」という語や花の名前が登場する歌は多く、本書における比率は実に9%にもおよぶ。第一歌集『亡羊』(短歌研究社、二〇〇七年)では4%、第二歌集『男歌男』(短歌研究社、二〇一七年)では6%なので、「花の歌が多」くなっていると言える。 一方で本書は、こういった歌から始まる。 ・鏡の奥にひと月ぶりの髭を剃る 空には竜の匂いがした ・青空の端をつかんで顔をぬぐう 洗面台に穴ひとつある ・大空に感情移入が立ち尽くす 光の針が降れば春雨 ・にんげんの心は退化してゆけよ 石割れば石あたらしくなる この四首は本書巻頭に置かれた「光の針」という連作である。一首目から三首続けて「空」が出てくる。歌集の冒頭から立て続けなので、空の印象が強くなるが、その後も「空」という文字や空を想起させる歌は数多く置かれている。「青空」や「大空」も含めて「空」が登場する歌は本書の7%を占め、「月」や「夕暮れ」など空の様子を感得できる歌を含めると16%にものぼる。花だけでなく、空のイメージも強い歌集だという印象だ。ちなみに歌集別に「空」(もしくは「そら」、単に空中を指すものや、「から」の意味で用いられているものは除く)という文字の使用割合を比較してみると、『亡羊』では5%、『男歌男』では3%であり、本書ではその使用頻度が上がっていることがわかる。 これまでの歌集でも見られたが、奥田の空の歌には、地上と空とのつながりが強く感じられるが、本書ではその色がさらに濃くなったようだ。前掲一首目では地上で刃物を持つ作中主体が感じている不穏なものとの距離感を「空」を用いて表している。久しぶりに「髭を剃る」時にシェイバーに感じる重たさと「竜」の重々しさが響き合う。二首目は距離感のある不穏な「空」を強引に「端をつかんで」引き寄せ、「青空」としてより具体的に把握し、地下へとつながる「洗面台」の「穴」との対比を描いている。まるで天国と地獄の邂逅のようにも思える。三首目は主体の感情が裏切られた様を「大空」でダイナミックに捉え、「感情移入」が「光の針」や「春雨」といった鋭くて繊細な涙に変わったかのような印象を与える。そして、四首目で前の三首を引き受け、感情がある意味「退化」して「あたらしくなる」ことは、死に近づいていくことと無縁ではないような感覚を生んでいるようにも思う。空の不穏さが、近くはないが遠くはない、言い換えれば見えているが手の届かない主体にとっての死という概念として描かれているように感じるのだ。地上と空のつながりとは、生と死の引き合いなのだろう。 ・老いゆけば後前おぼろ いちめんの花野を這うているばかりなる この歌は本書の五首目に置かれており、「光の針」の次の連作「いのちの湯気」の一首目である。本書に「花」が初めて登場する歌でもあるが、ここでは「花野」が死を前にした世界としてイメージされている。同じ連作にはこういう歌もある。 ・同心円の半分は海、半分は花野。 子どもが老いて生まれる やはりここでも「花野」は老いの象徴であり、死の手前の地上での最後の楽園のように読める。巻頭では「死」や「老い」と向き合うために、「空」や「花」が用いられているという印象を強くする。 すべての「空」や「花」がそのようなモチーフとなっているわけではないが、一冊の歌集として読んだ場合、巻頭での印象は忘れ難いものとなる。「空」を例に見てみたい。 ・青空ゆほとりほとりと虫落ちて 秋の野原の広々とある ・井戸のような心に歩む炎昼の 空に滑車のからからと鳴る ・庭の草空へ空へと枯れゆくを 石に座りて日がな見ており いずれも空=死と地上=生とのつながりとして読むことができ、二首目などは「井戸」の「滑車」が「空」とつながっていることにより、死に導かれることを意識した「心」を表したとも言えるだろう。 本書には二行分かち書きになっている歌が多いが、奥田はあとがきにこう書いている。 ・基本的に作品は二行分かち書きにした。読みやすさに配慮した結果だが、制作時期の比較的早い第三章の作品は、構成上の変化をつけるために一行表記のままにした。虚構性の高い作品を二行に、私性の高い作品を一行にというイメージがなかったわけではないが、さほど厳密なものではない。「私性」は、ここでは「私の中に深く沈んだもの」というほどの意味合いである。 ここまで引いてきた歌はすべて二行分かち書きだが、あとがきによると、それらは「虚構性の高い作品」である可能性が高いようだ。確かに抽象性に富み、現実の写実という意味での「私性」とは離れた地点から生と死を見つめているようにも思える。しかし同時に、これらの作品には、奥田の死生感が色濃く反映されていると感じる。それも「私の中に深く沈んだもの」に違いない。 「私性」の観点でいうと、本書にはもう一つ紹介しておきたい試みがある。二つの連作においてボカロP(合成音楽ソフトを用いてボカロ曲を制作する音楽家)のtamaGOとの合作二十七首を発表しているのだ。何首が引く([]内はtamaGO作) ・青空ごと蛇は小鳥を呑みこみぬ [生命体である以上あなたと体内外] ・革靴の中に踏み抜く空がある [本気で茶番しろよと思う] ・[髪がびしょびしょのままカロリーメイト食べてる] 竜の匂いが空にただよう ここにも奥田作の部分には「空」がよく登場している。一首目、「蛇」は「青空」=死もろとも「小鳥」を「呑みこ」んでいる。tamaGOの下の句が個体の別という概念でそれを受けている。二首目、「革靴の中」という見えないところで死である「空」を「踏み抜く」ことに対して、下の句で檄を飛ばす。どうせ死ぬのに懸命に生きるという「茶番」が美しい。三首目、「カロリーメイト」という生きるためだけのような食べものと死のイメージ。ここでも「空」と「竜の匂い」が再び組み合わさる。 これらの上の句と下の句の響き合いは意外性に満ちており、奥田単独の作品とは趣の異なる説得力が生まれている。この意外性からくる説得力という詩情は、合作ならではのことと言えるのではないか。 こういった合作は、漫画、脚本、楽曲、美術などでは多いが、短歌ではほとんどない。しかし、このように合作からは一人の「私性」を前提としない新しい詩が生み出される可能性も感じることができた。 いずれにせよ、単独作でも合作でも生と死の引き合いが随所に見られる本書は、奥田の一貫した死生感が反映された一冊だ。地上に咲く花は老いるまで現世に満ちるものであり、それは常に太陽がある空を向いている。私たちは空を見上げて生きているのだ。 ・フラワーなビューティフルなり 青空の下であなたと抱き合っていた 奥田のどこまでも俯瞰を忘れない態度に、ふと立ち止まり、自分の現在地を確認した。 (現代短歌2022年7月号掲載) *『花』は砂子屋書房刊
続きを読む